石井健雄氏は「Takeo Ischi」として有名になる前の15歳の時、日本でヨーデルを始めました。趣味が高じて職業となり、ドイツ語圏の民族音楽界で名が知られるようになり、最近ではインターネットを介して国際的にも有名になりました。引退後もヨーデルを続け、YouTubeでは「Chicken Attack」という曲が2500万回再生を超えるなど、一躍スターになりました。しかし日本の機械工学の企業家の息子である石井氏にとって、日本から欧州に渡る決断は決して簡単なものではありませんでした。J-BIGは、一風変わった職業に就く石井氏にドイツでのチャンスがどのように生まれ、どのようにプロのヨーデルとして生計を立てていたのか、労働許可証の取得の際の苦労、経済状況の変化、そしてYouTubeで若い世代にブレイクするまでの経緯についても併せてお話を伺いました。

――日本人のヨーデル歌手としてすでに何十年以上も前からドイツで有名ですが、どのような経緯で日本人である石井氏が、この一風変わった職業に就こうと思ったのでしょうか?
石井健雄:もともとは、日本で家業を継ぐために機械工学を学ぼうと思っていました。父はエンジニアで、麺を乾燥させる機械を作る会社を経営しており、私は幼い頃から会社を手伝っていました。そんな中、たまたまヨーデルを発見し、日本でこの趣味を追求しました。
子供の頃、ラジオでヨーデルを聞いたことはありましたが、それが何なのかはよく知りませんでした。当時はヨーロッパアルプスのヨーデルと、カントリーミュージックに登場するカウボーイのヨーデルの2種類しかないと思っていたのです。日本で最も有名なヨーデル歌手は、日米にルーツのあるカントリー歌手、ウイリー沖山でした。父の同僚の好意で、たまたま彼のレコードを手に入れることができ、すぐに彼のヨーデルの歌声の虜になりました。中学の卒業旅行で京都と奈良に行ったとき、同級生が小さな歌集をつくってくれたんです。その中に、日本で一番有名なヨーデルの歌である「山の巾着物」という歌がありました。この歌のヨーデルの部分をウイリー沖山が見事にヨーデルしたのをきっかけに本格的にヨーデルに興味を持ちました。
無料メルマガ会員登録
『J-BIG – Japan Business in Germany』は、ドイツで活躍する日本企業や日本関連ビジネスに関する情報をお届けするメールマガジンです。
そして6年生になって初めて学校の合唱団に入りました。音楽が好きで、子どもの頃からいろいろな楽器に興味がありました。でも歌はあまり得意では無かったですね。いつも音程を外して歌っていたので、もっとうまくなりたいと思っていました。そんな時、クラスメートが楽しそうにヨーデルを歌っていて、「あ、日本人もヨーデルができるんだ!」と気づかされました。それ以来、本気でヨーデルを覚えようとしたんです。ウイリー沖山のテープを録音して、彼のヨーデルを真似をすることから始めました。最初はとても苦労しましたね。何週間も犬のように吠え続けていました。そこで私は、胸声と頭声とがどこで始まるのかがよくわかるように、テープをゆっくり流すことを思いつきました。チェストボイス(胸声)とヘッドボイス(頭声)の切り替えは、ヨーデルの中心的なテクニックだからです。そうしているうちに、自分のヨーデルが上達していくのを実感するようになりました。練習を重ねるうちに、ヨーデルの技術のひとつである「Kehlkopfschlag」を習得することもできました。とても嬉しかったですし、この最初の成功が、ヨーデルを続けるモチベーションになりました。
その後、バイエルンのヨーデル歌手、フランツル・ラングのレコードを手に入れました。それがとても美しかったんです!その日以来、私はより一層ヨーデルの世界にのめり込み、ラジオでヨーデルの番組を録音し、さらにレコードを集めました。そして、毎日数時間、勉強するときや寝るときに聴きました。美しい山々や新鮮な空気の中で奏でられる音を聴き、いつか実際にヨーロッパアルプスの地に立つことを夢見ていました。これが、私とヨーデルとの始まりです。

――日本では珍しい趣味だったのでは?
石井健雄:そうですね。音楽にはもともと興味がありましたが、歌は残念ながら得意ではなかったので、少しヨーデルができたときの喜びはひとしおでした。しかし、すぐに趣味を仕事にしたわけではありません。18歳のとき、東京の東海大学で機械工学を学び始め、ヨーデルには山歩きが似合うと思い、大学のハイキングクラブにも入りました。勉強以外の時間はレコード探しに費やすことが多かったですね。買い物をしているときに、たまたま「はじめてのヨーデル」という本を見つけ、買ってみると、その店の主人が東京のヨーデルクラブの名誉会員であることが発覚しました。そのクラブはドイツ語で「Alpen-Jodler Kameraden」という名前で月に一度、ヨーデルを歌いながらドイツ語を学ぶという活動をしており、私はすぐに会員になりました。当時すでに60人の会員がいて、比較的ヨーデルが上手な人が多かったんです。私はとても恥ずかしがり屋で、みんなの前でヨーデルをすると、顔が真っ赤になってしまうほどでしたが、時間が経つにつれてだんだんと慣れていきました。
ある日、アウグスブルクからドイツ人の留学生がヨーデルクラブにやってきました。すぐに友達になり、彼女は週に一度、私にドイツ語を教えてくれるようになりました。この交流がきっかけで、私はますますヨーロッパ、特にアルプスの国へ思いが強くなっていきましたが、海外滞在には高い費用がかかることは知っていました。そんな時、そのドイツ人留学生が、「ドイツに旅行に行くなら、私の実家に泊めてあげるよ」と言ってくれたのです。私はすぐに渡独の準備を始めました。1973年10月7日、羽田空港を出発し、モスクワを経由してパリへ、そしてパリからアウグスブルクへ。当時はドイツ語も英語も少ししかわからなかったので、全てがアドベンチャーでしたね。そしてアウグスブルクに着くと、滞在する予定だった家には空き部屋がないことが分かりました。私は「こんなはずはない!」と焦りましたが、幸い、日本で知り合った学生が、クラスメートの家族が所有する学生用フラットに、無料で部屋を用意してくれたのです。比較的広い部屋で、シャワーも完備されていて、そのクラスメイトの家族と一緒に食事をすることもできました。唯一の心配は家賃をどうやって払うのか。でもその家族は、日本の切手集めや庭仕事を手伝えば、何も払わなくていいと言ってくれました。クリスマスもその家族とお祝いし、たくさんのプレゼントを貰い、そしてそこで初めてバイエルンのレーダーホーゼ(ドイツ南部バイエルン州からオーストリアのチロル地方にかけての地域で男性に着用される肩紐付きの皮製の半ズボンのこと)を手に入れました。
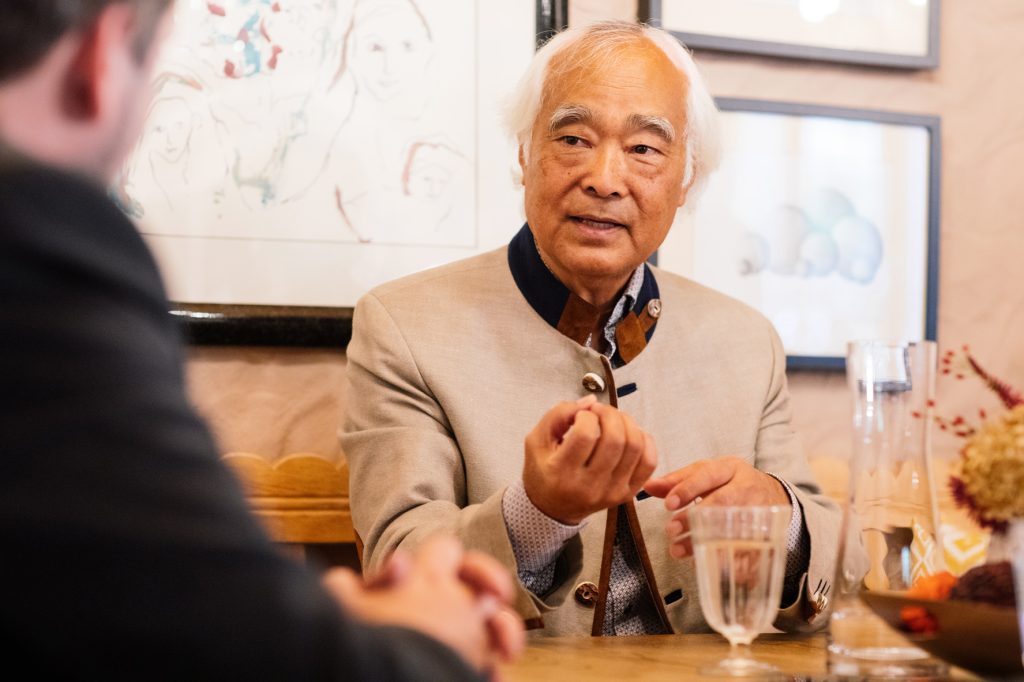
当時は、自分のヨーデルがどれほどのものなのか、よく分かりませんでしたが、ヨーデルで人を喜ばせることができることにすぐに気がつきました。それもあって私はずっとヨーデルを楽しんでこれたのです。私の誕生日に、バイエルンのヨーデル王フランツル・ラングに直接会う機会があったんです。私は彼からヨーデルのテクニックを学びたいと強く思っていたので、アコーディオンを手に取り、ヨーデルを披露しました。マスコミも来ていて、翌日には「日本人のヨーデル歌手がバイエルンの女の子を探している」と報道され、それでちょっと有名になったんです。それから音楽グループで活動している知人の紹介で、カーニバルでステージに立ってヨーデルを披露する機会がありました。それがお客さんに好評で、「明日から俺たちと一緒にやろう。食事もお小遣いももらえるよ。」と声をかけてくれたんです。その日から私は毎日、レーダーホーゼを履き、ズボンのポケットに嗅ぎタバコの布を入れてステージに立ち、ヨーデルを歌いました。これが私のヨーデルのキャリアの始まりでした。

――本来、ヨーロッパは観光の目的で訪れたのでは?
石井健雄:当時、私はもう少しドイツに滞在する方法を探していました。実は、ここで機械工学の勉強を続けながら、仕事もしたかったのですが、就労や就学の許可が下りなかったんです。そこで、語学留学生として6カ月間の滞在許可を得ました。この間、市民学校の語学コースに通ったり、ダンスのレッスンを受けたりしました。しかし6カ月が過ぎ、出国の日が近づいていました。そんなある日の帰り道、チューリッヒで、日本のヨーデルクラブで知り合った友人を訪ねました。幸運なことに、その頃チューリッヒでは「ヨーロッパ・イン・チューリッヒ」と呼ばれる大きなフェスティバルが開催されていました。そこには大きなテントがあり、バンドが演奏していました。友人から「タケオ、君はヨーデルができるんだ。ステージに上がってみたらどうだ」と言われました。そこで私はヨーデルを歌い、夜はレストランで演奏したのですが、観客からの評判がよく、レストランの社長が「部屋代と食事代と小遣いで、毎日そこでヨーデルをやってもいいよ。」と言ってくれました。それで、数週間滞在することができ、旅費を節約することができました。機械工学の勉強はすっかり忘れていましたね。
「ヨーデルで少しは稼げるから、やれることを今のうちにやっておこう」と思ったのです。やがて、マスコミに取り上げられるようになり、ラジオや新聞の取材を受けるようになりました。その2カ月後、テレビ出演のオファーがありました。土曜日の夕方、ゴールデンタイムに、スイスのテレビで13分間、生演奏を披露しました。出演は大成功、数日後、あるレコード会社から、私と契約を結びたいという電話がかかってきました。
――それはいつでしたか?
石井健雄: 1974年、27歳のときです。チューリッヒのランチで知り合った友人がスイスのドイツ語を教えてくれて、レコード会社のHelvetiaと契約することができました。そしてその後、2枚のシングルレコードをリリースすることができました。

――レコードの売れ行きはいかがでしたか?
石井健雄: それは判断し難いですね。私のライブの後はよく売れました。でも何枚売れたかはお店の人に聞いてもわからないんですよね。それでも、自分のレコードが店頭に並んでいるのを見るのはとても嬉しかったです。
その後滞在許可証のために、通訳学校に1年間通いました。その間多くのライブをこなしましたが、労働許可証を持っていなかったので、決まった契約はありませんでした。そのため、お小遣いや旅費をもらって出演する毎日が続き、一年後何をしているのか、どうなるのかとても不安でした。そしてまた、ヨーデル歌手として雇用されるにはどうしたらいいのかもわかりませんでした。ところが、私を発掘してくれたレストランの社長が、スイスの正式な労働許可証を取得するのを手伝ってくれたんです。これで1975年5月から正式に働けるようになり、雇用契約も結べるようになりました。こうして正式な労働契約を結び、私はプロのヨーデル歌手として働けるようになりました。
――1970年代半ばのヨーデル歌手としてのお給料はどのくらいでしたか?
石井健雄:最初の頃、カーニバルのステージで楽しくヨーデルをしていた頃は、当時は3曲、合計10分でしたが、50マルクの小遣いとタダ飯がもらえました。それで旅費をまかない、2週間毎日演奏して少しずつお金を貯めることができました。チューリッヒでも、最初のうちは1回の仕事で50フラン、それに部屋代と食事代がもらえていましたが、正式に仕事が許されるようになると、最初は200フランだったものがどんどん上がっていって、何年か後には800フランになりました。音楽事務所と契約すると、出演料は1回1000フランでしたね。平均すると、月に2、3回のライブがあったかな。ブッキングが多い月もありましたが、ライブがない時期もありました。合計スイスには6年間住んでいました。

――日本の両親はプロのヨーデル歌手としての活躍について何とおっしゃってましたか?
石井健雄: 私の両親、特に父はとても心配していました。そんな両親を安心させ、勉強を続けていることを信じてもらうために、最初のうちは機械や道具のカタログを送りました。また、私の活躍を伝える新聞記事も同封しました。そうしているうちに、両親は私がヨーデルで成功していることに気づいてくれました。そして私のヨーデルのキャリアが並大抵のものでないことにも理解してくれ、最終的に両親とも、私のヨーデル歌手という職業を認めてくれました。とても嬉しかったですね。

当時、私にはスイス人の彼女がいて、その彼女を家族に紹介するために、日本に飛びました。家族は、私がスイスで仕事や友人と充実した生活を送っていることを知り、安心したようです。私にとって、スイスは世界で最も美しい国だったので、この生活を続けない理由はありませんでした。機械工学を学ぶということはいつの間にかすっかり忘れていましたね。

――ということは1973年と1974年が石井さんの運命を分けた年ということになりますね。
石井健雄: 当時、転職の決断はそれほど難しいものではありませんでした。しかし頭のどこかではいつも「いつまでこんなことを続けていられるのだろう。いつかは終わって新しい仕事を探さないといけないんだろうな。」と思っていました。そんな不安とは裏腹に私のギャラはどんどん上がり、一回のパフォーマンスで1800フラン稼げるようになりました。1978年オイグスター社で初めてレコードとカッセト「Der jodelnde Japaner」を制作しました。その後スイスに支社を持つ日本の会社の「スイスの民族音楽グループと一緒に日本ツアーをしたい」というのがきっかけで、1979年に二週間の日本ツアーが実現しました。私は歌とヨーデルを担当しました。本物のスイス人と共演したことで、日本の観客は私のヨーデルを本物だと感じてくれ、ツアーは大成功に終わりました。これがきっかけで日本での知名度も上がり、レコードとカセットもとてもよく売れました。
ツアーガイドをしていた知人を通じて、私のレコードはマリア・ヘルヴィッヒの手に渡りました。彼女は当時、ドイツ公共放送連盟ZDFで3つの番組のプレゼンターをしており、1980年に私は彼女の番組のひとつである「Früh übt sich」に招待されました。そして後日、番組が大成功だったと連絡がありました。マリア・ヘルヴィッヒとはそれからも連絡を取り合い、休暇に招待してくれる仲になり、スイスでの仕事についてもいつも気にかけてくれました。スイスは国土が狭く、演奏の機会は限られているので私はすでにほとんどのすべての場所で演奏していました。すると、マリア・ヘルヴィッヒの夫が、ドイツで私の労働許可証を申請してくれたのです。1981年5月、私はドイツで歌手として労働許可証付きのビザを取得することができました。

――就職先はどこでしたか?
石井健雄:ヘルヴィッヒ家のレストラン「Kuhstall」に就職しそこで、常用ヨーデル歌手として働いていました。月給と1日3食の食事がもらえ、時にはバーを手伝い、スタッフともだんだん親しくなっていきました。その中には、後に私の妻となる素敵なシェフもいました。マリア・ヘルヴィッヒとは、一緒に定期的にテレビに出演する機会も増え、オーストリア・リンツのラジオ局にも連れて行ってもらいました。そこで出会ったのがカール・モイクでした。そして彼の好意でMusikantenstadlという番組にも出演することができました。当時はテレビ局が3つしかなかったので、出演することですぐに目立つようになりました。1984年、私は初めてのドイツツアーを行い、1988年までマリア・ヘルヴィッヒの社員として毎年さまざまなツアーに参加しながら働きました。しかし唯一の問題が名前でした。有名になり注目されることが多くなったのですが、なかなか名前を覚えてもらえませんでした。そこで自分の名前の発音を分かりやすく変えれないか考え、Takeo IshiiではなくTakeo Ischiと表記することにしました。
その後、ヘルヴィッヒの仕事を辞め、自分のビジネスを始め、バイロイトにオフィスを構えました。その時にはもう無期限の滞在許可証と労働許可証を取得することができました。
――1990年代、民放テレビがテレビ界に革命を起こし、メディアの状況は劇的に変化しました。この間どのように物事が進んでいったのでしょうか?
石井健雄:テレビに出演するすべてのアーティストにとって大きな問題でした。民放は番組数が多いので、より多くのアーティスト、それも無名のアーティストが招かれ、出演料が下がり、経費がかさんでいきました。民放への思い入れは薄かったですが、ライブを断るという選択肢はなかったです。いつまた呼ばれるかわからないので、ギャラは安くても全部引き受けました。また、公共放送では収入が少なくなりましたね。以前は1曲で2,000マルクももらえたのに、長い演奏でも500マルクしかもらえなくなりました。それに加えてマルクからユーロへの移行もあったのですが、賃金が調整されるまでには長い時間がかかりました。2008年の金融危機は、さらなる困難に直面し、イベントの数は減り、給料はさらに減りましたが幸いなことに、事務所が十分なイベントを用意してくれていたので、大きな不自由を経験することなく危機を乗り切ることができました。
実は、65歳で年金生活を始めることをきっかけに退職したんです。私のCDを制作しているレコード会社、Rubin Recordsとまだ契約が残っていましたが、幸いにもライブの需要が高いこともあり、退職後も楽しく演奏を続けることができました。

――最近、インターネット上で一躍時の人になったと聞きました。特に新曲はYouTubeで何百万回も視聴されていますが、一体どのようにして生まれたのでしょうか?

石井健雄:最初は私が意図してやったことではありませんでした。誰かが私の曲「Bibi-Hendl」をYouTubeにアップロードし、そしてその動画が短時間で世界中からアクセスされ、私は話題の人になったのです。YouTubeでお笑い音楽を専門に扱うグループ「The Gregory Brothers」も、それがきっかけで私の存在を知りました。私のミュージックビデオ「New Bibi-Hendl 」では、私は手にニワトリを持っており、グレゴリー・ブラザーズはこのモチーフを起点に、僕と一緒に「Chicken Attack」という曲を作りました。ミュージックビデオでは、革のズボンを履いて、手に白いニワトリを持ち、それが忍者に変身するのです。視聴回数は、最初は1回、次は2回、そして1,000万回と、どんどん増えていきまいした。今まですでに2500万回の再生を超え、アジア全域でも人気が出ました。2019年には、台湾のヘビーメタルバンドのライブに採用され、この曲がメタルバージョンでカバーされたりもしました。
――ということは、引退後もインターネットで活動の幅を広げられていったのですね。
石井健雄:YouTubeやインターネットは、プロモーションのための絶好の機会を提供してくれます。「Takeo Ischi」で検索すると、イベントや演奏の写真や動画がたくさん出てきます。その結果、近年、若い人たちにも知られるようになりました。でも私は昔から私生活のすべてを公開しないように気をつけてきましたので、フェイスブックのアカウントも持っていません。なので幸いなことに、安心して老後を過ごすことができてきます。いまは毎月わずかな年金をもらっています。たいした額ではないですが、幸いにも私は持ち家があり、子どもたちもすでに成人しています。妻もまだ働いてお金を稼いでいるので、庭の手入れや家事は私がやっています。洗濯、食器洗い、アイロンがけ、家の掃除、それから庭の枝切りや、掃き掃除など、大変な作業ですが、それが毎日の日課なんです。時には家で静かな時間を過ごし、自分の趣味を追求することもあります。YouTubeを見たり、手芸をしたり、楽器を演奏したりすることが多いですね。もちろん、ボイストレーニングもしますよ。毎日やることがたくさんあって、年金生活者としてはまったく飽きないですね。時々、演奏や取材の依頼があり、いまでも多くの国を旅する機会があります。ドイツやヨーロッパだけでなく、YouTubeのおかげで世界中に知られるようになりました。
今となっては私は数少ない現役のプロヨーデル歌手の一人です。確かにパートタイムでヨーデルをする人はまだいますが、プロとしてフルタイムで活動する人はもういないでしょう。生活し、税金を払い、年金を納めるにはたくさんのライブをこなさなければなりませんが、今の時代、それはなかなか難しいことです。有名なプロのヨーデル歌手はみんな亡くなってしまって、次の世代がいないんです。ヨーデルへの関心も薄れ、アマチュアのヨーデルだけではキャリアにならなくなってきました。

――今でも演奏したり、コンサートを開いたりしていますか?
石井健雄:コロナ禍を経て、イベントの数は減りましたが、基本的には今でも演奏しています。昨年7月にはZweibrücken(ツヴァイブリュッケン)の町のお祭りに出演し、1時間ヨーデルを披露しました。
――どのように今でも演奏はこなしているのですか?
石井健雄:今でも何とかやっていますが、公演の回数は減らしました。月に一度でも演奏できることが私の幸せです。

――ドイツと日本には、大きな文化の違いがあります。そんな中、ドイツに馴染み、まさにドイツ的なキャリアを築き、成功を収めてきましたが、海外での成功の決め手は何だったのでしょうか?

石井健雄:一般的に、日本人は控えめな人種です。一方、ヨーロッパでは、自分の気持ちを比較的オープンにする人が多い。ボディーランゲージが重要な役割を果たし、自分の考えを自由に話すことができます。日本では、自分の意見が本当に求められているのかどうか、考えすぎてしまうことが多いと思います。でもこの遠慮こそが、個人の成長や環境との健全な関係を妨げていると思います。もちろん、親しみやすさは大切ですが、遠慮を取り払い、新しいことに挑戦することも大切なことです。例えば、新しい言語を学ぶこと。ドイツ語だけでなく、方言も学ぶことで、まったく違うチャンスや人間関係が広がりました。それはヨーデルにも言えることです。見せかけだけではいけない。スイスのヨーデル、バイエルンのヨーデル、オーストリアのヨーデルなど、本物のヨーデルを学ぶことで、どこでも受け入れられ、地元の人たちとも親しくなれます。順応性は重要な要素です。しかし、自分の意見を伝えることも同じように重要です。親しみやすさ、寛容さ、理解力、そして新しい視点を受け入れることで、立ち止まることなく、人間として成長することができるのです。



